「のと里山里海カフェ」に参加しました
- 2025年7月25日
- 読了時間: 2分
7月25日(金)
7月20日、金沢大学先端観光科学研究所の菊地直樹教授にお招きいただき、「のと里山里海カフェ」に代表の佐竹が参加し、豊岡でのコウノトリ野生復帰の取り組み状況を説明してきました。
場所は、能登町の当目地区多目的研修集会センター。当日のテーマは、「トキ、コウノトリと共生する地域づくり」です。

能登町は、ほとんどが山あいの細長い谷の中に民家が少数ずつあり、集会センターもひっそりと建っていました。実は、菊地先生から話をいただいたときに思ったのは、地震と洪水被害で大変な目に合われている能登半島にも拘わらずコウノトリが4カ所も繁殖しているので、ぜひ地域の復興にコウノトリから力をもらってほしいと思い、そのことを訴えたいと思いました。
実際に行ってみると、センターの壁は剝がれて落ちたままだし、室内のエアコンも修理されていない状態です(そのため蒸し暑い中でのカフェとなりました)。それでも皆さん来年にトキが放鳥されることもあり出席者は30人と多く、関心は高く和やかに懇談できました。出席者の感想は、菊地先生のブログをご覧ください。

せっかくの機会だからと、珠洲市自然共生室の宇都宮大輔さん、当会会員の木村透さんの案内でコウノトリの様子を見てきました。
〇河北潟 早々と巣立ちし、周辺に親子とも姿は見えませんでした。
〇羽咋市 トキの放鳥に備えて、ビオトープ田2枚ができていました。なんと、コウノトリの巣塔も2基建っています。なんでも、市のまちづくり課が建てたとのこと。その近くの田んぼではコウノトリの独身組10羽前後が毎日滞在している(ねぐらは鉄塔)そうです。田んぼの畔を歩きましたが、餌生物らしきものは見つかりませんでした。なんでこの場所が気に入り、餌は足っているのかしら?

〇珠洲市 民家から離れた農地と耕作放棄地の中にある電柱で、J0447とJ0502が営巣し、J0952を育てていました。3日ほど前に足環が装着されたとのこと。当分、地域づくりには結びつかないようです。

〇能登町 残念ながら、営巣場所には行けませんでした。
全体として感じたのは、河北潟は当会が人工巣塔を建て、迎え入れ体制をとっていましたが、その他は何の準備もない状態で突如コウノトリがやってきて営巣したものです。地域の行政や住民が盛り上がらないのは当たり前です。
今後は、「いかにコウノトリ、トキの力を活用して地域を充実させるか」にかかっているように思います。
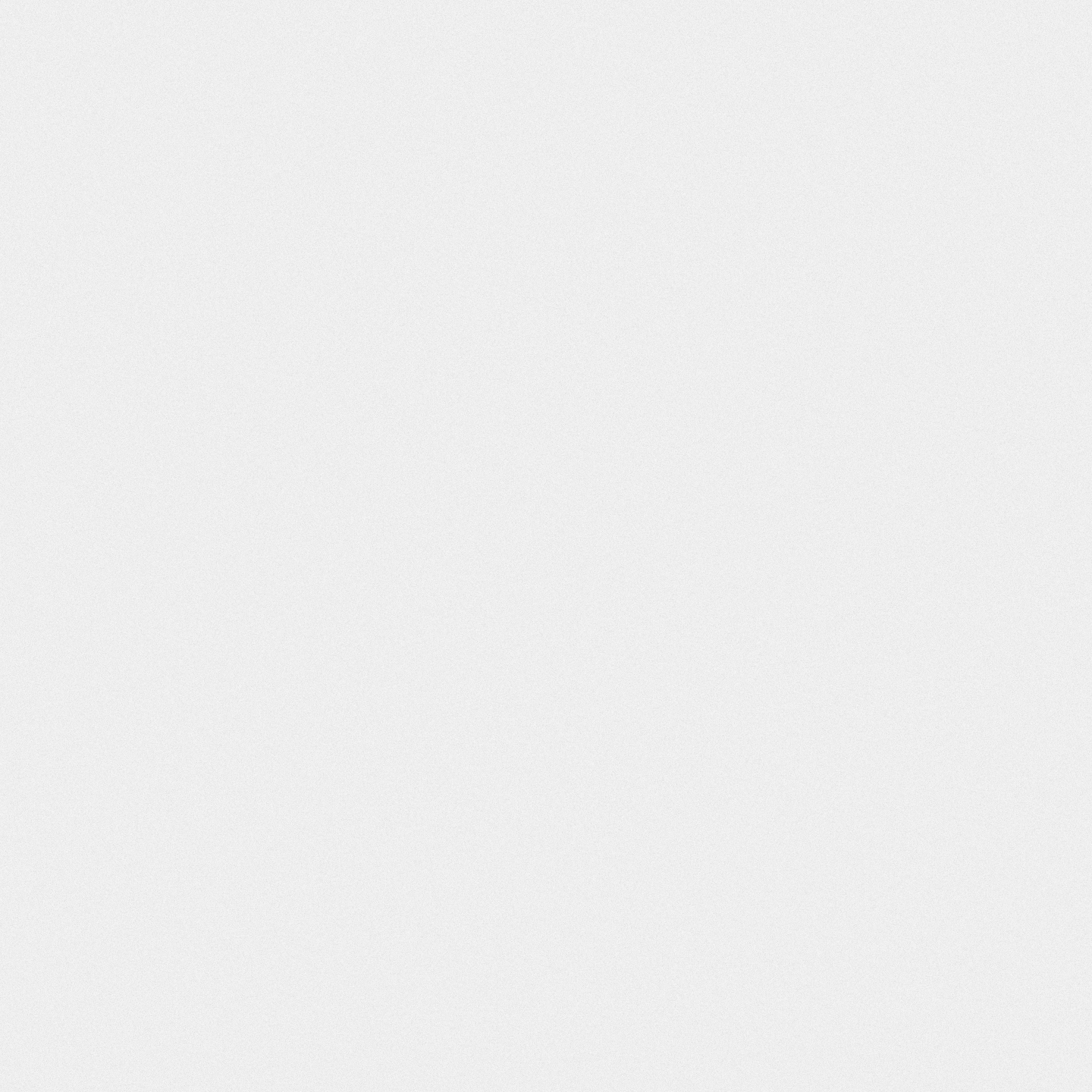









コメント